こんにちは、そうまです。
本日は『休養学|著者 片野 秀樹』の本を読んでの学びをシェアしたいと思います。
”休むこと=寝ること”ではありません。
とういう帯に目が止まり、購入しました。
みなさんも仕事や家事などで、色々と疲れがたまっていることと思います。
今回の内容が、少しでも疲れをとる参考になれば嬉しいです。
では、早速始めていきます〜。
日常のサイクルに「活力」を加えてみる
私の感覚では、今の日本人は休養しても50%程度しか充電できてないないイメージです。
そのまま活動して20%くらいまで減り、休養で50%にどうにか戻って、また活動して・・・。
これでは、私たちの消耗は進むばかりで、疲れがどんどんたまっていってしまいます。
そこで提唱しているのが、次の活動に移る前に、休養のほかにもう一つ、疲労を打ち消すような要素「活力」を加えることです。
つまり、休養した後すぐに活動を始めるのではなく、そこから更に活力に満ちた状態まで持っていき、再び活動する、というサイクルです。
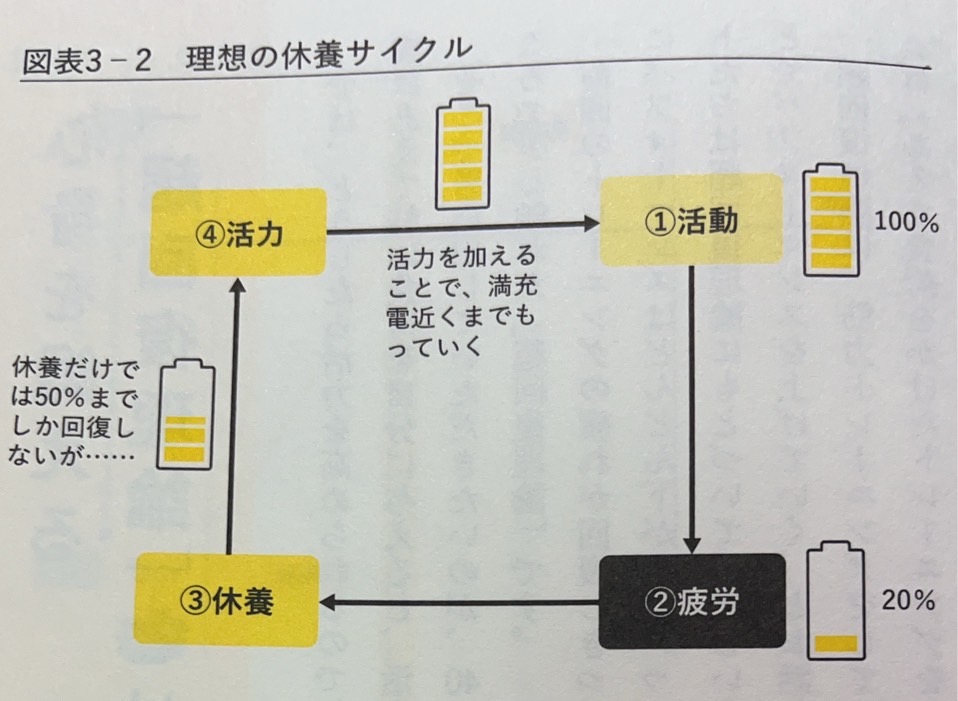
休養だけでは50%程度しか充電できなくても、活力を加えて満充電に近いところまでもっていくのです。
7つの休養モデル
この7つのモデルを日常に取り入れることで、疲労回復は促進されます。
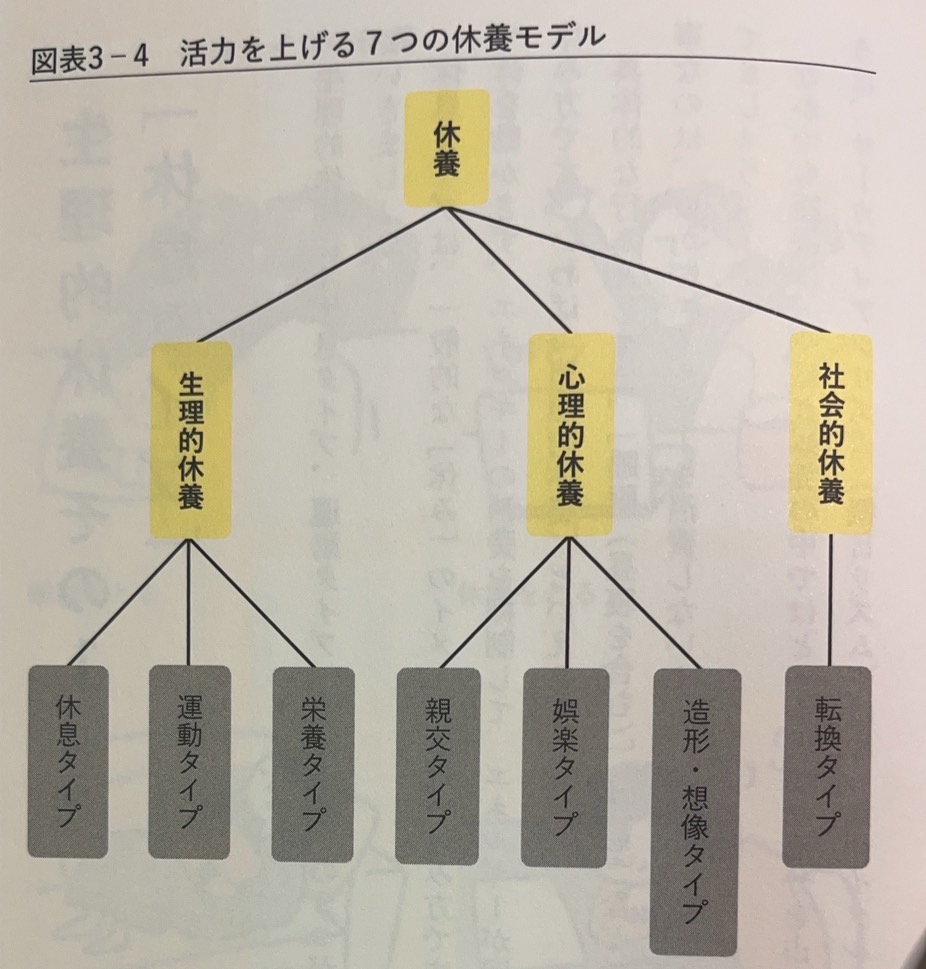
《生理的休養》①休息タイプ
- 睡眠をとる
- 休憩をとる
- ソファでゴロゴロ
活動を一旦中止し、エネルギーの消費を抑えてリラックス。
《生理的休養》②運動タイプ
- ウォーキングする
- 体のストレッチする
- 軽く運動する
老廃物の除去やリンパの流れをよくすることで疲労感を軽減する。
《生理的休養》③栄養タイプ
- 食事量を抑える
- 胃腸にやさしい食事をとる
- 白湯で体を温める
食べる量や回数を抑え、疲れた消化器系を休ませる。
《心理的休養》④親交タイプ
- ペットと触れ合う
- 挨拶を交わす、雑談をする
- 自然に触れる、森林浴
社会や人と交流したり、自然や動物と触れ合ったりする。
《心理的休養》⑤娯楽タイプ
- 音楽鑑賞や映画鑑賞
- 推し活
- 本を読む
自分の趣味や嗜好を追求する。ちょっとした気分転換でもかまわない。
《心理的休養》⑥造形・想像タイプ
- 絵を描いたり詩をつくったりする
- 日曜大工やDIYをする
- 瞑想する
何かに集中したり、好きなことに思いをめぐらせたりすることで疲労感が軽減する
《社会的的休養》⑦転換タイプの休養
- 洋服を着替える
- 部屋の模様替えをする
- 旅行に行く
外部環境を変化させることで、気分をリセットする。掃除でもよい。
大事なのは7タイプを組み合わせること!
それぞれの休養タイプを複合的におこなうことで、疲労回復効果が2倍にも3倍にもなるのです。
睡眠は活力のカギ
いうまでもありませんが、睡眠は疲れをとるために必要不可欠なものです。
睡眠をとらないと最終的に人間の体は壊れてしまいます。
睡眠の大事な役割の一つは、なんといっても細胞の修復です。
昼間の活動で傷ついた細胞の修復が、主に睡眠中におこなわれます。
厳密にいえば昼間でも細胞の修復はされてます。
しかし昼間は体を動かすほうに酸素が優先的に使われるので、あまり細胞の修復には手がまわりません。
その点、睡眠中は消費する酸素が少なくて済むので、細胞の修復に酸素を使うことができます。
細胞の修復を助ける成長ホルモンも夜、寝ているときに分泌されるので、眠ると疲れがとれるのです。
(※さらに、記憶の定着や整理も睡眠中におこなわれます。)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
睡眠を十分にとり、7つの休養モデルを組みあわせて「活力」をつけていきましょう。
バランスが何より大事な気がしています。
上手に疲れをとって、元気に楽しく過ごしていきたいですね!!
ありがとうございました。
引用:『休養学|著者 片野 秀樹』





コメント